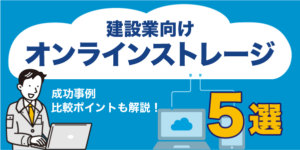人手不足や高齢化、10年以内の大量離職など建設業界ではさまざまな問題があります。
しかし「労働基準法改正」の改正により、建設業界の働き方が大きく変わるかもしれません。
今回はそんな「労働基準法改正」についてご紹介していきます。
正しい知識を身に付けて、建設業における残業時間の上限規則について理解しましょう。
目次
1.残業時間の上限規制とは
2.建設業における働き方の現状と課題
3.建設業の残業規制改正で何が変わるのか
4.建設業の残業規制へ対応するための4つのポイント
5.建設業で残業規制以外にも注意すべき変更点
6.建設業における残業規制についてQ&A
7.まとめ
1.残業時間の上限規制とは

時間外労働(残業)の上限規制が行われる背景には、女性のキャリア形成、少子化対策、仕事と家庭の両立などがあります。
日本が直面している少子高齢化に対する対策として「働き方改革」があり、その一環として労働基準法が改正され時間外労働が規制されました。
①労働時間の大原則
まずは、法定労働時間について現行ルールをご紹介します。
・1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない
・6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけない
・毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけない
参考:建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省
②「36協定」で定める時間外労働の上限
ただし、上記の法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や、休日労働をさせる場合には次の手続きが必要です。
・所轄労働基準監督署⻑への届出
参考:建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省
多くの企業に時間外労働や休日労働があるのは、事前に上記手続きを行っているからです。
繁忙期など、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を⾏わなければならない場合には、2019年までは「特別条項付きの36協定」を締結すれば、実質上限なし(年6ヵ月まで)で時間外労働を⾏わせることが可能でした。
しかし2019年4月の労働基準法改正で、臨時的な特別の事情があった場合(特別条項)でも残業時間の上限が定められました。
既に大企業では2019年4月から、中小企業は2020年4月から施行されていますが、時間外労働や休日労働が恒常化している建設業に関しては、新ルールの適用まで5年の猶予が設けられていました。
新ルールの適用は、2024年4月1日に始まります。つまり建設業にも、時間外労働の上限規制が適用されるようになるのです。今後は原則として、月45時間・年360時間を超える時間外労働ができなくなります。
この変更に伴い、建設現場ではさまざまな課題が生じると考えられています。総称して「建設業2024年問題」と呼ばれており、問題を解決するには上限規制の適用を見据えた働き方改革の実行が急務です。
関連リンク: 建設業の2024年問題とは?影響や対策をわかりやすく解説③建設業に5年の猶予期間が設けられた理由
なぜ建設業では残業規制適用に関して、5年間の猶予期間が設けられたのでしょうか?
その答えは、建設業においては時間外労働や休日労働が恒常化しており、さらには人手不足で、現場におけるさまざまな課題をただちに解決するのは困難だと考えられたためです。
建設業における働き方の現状と課題については、次章で詳しく見ていきましょう。
2.建設業における働き方の現状と課題
建設業において残業時間が長くなってしまう理由や、働き方改革がなかなか進まない理由について、データとともに掘り下げます。
①全産業と比べて90時間長い労働時間
次に示す国土交通省のグラフは、産業別の年間実労働時間を示したものです。
建設業は黄色の折れ線グラフによって表示されています。
2021年の建設業における年間の実労働時間は全産業と比べて90時間も長く、20年前と比較して労働時間の減少幅が小さいことが読み取れます。
 出典: 建設業を巡る現状と課題|国土交通省
出典: 建設業を巡る現状と課題|国土交通省
建設業においては、あらかじめ定められた工期内で現場の施工を完了する必要がありますが、天候によって進捗が遅れるケースも多々発生します。
9月末や3月末の決算月が繁忙期に該当するなど、年間を通して労働時間が長くなる要因が数多く存在しています。
②労働者数の減少・高齢化が進行
建設業に従事する労働者数が減少し、高齢化が進行している点も課題のひとつです。国土交通省のデータから、建設業における労働者数の推移や高齢化の進行状況を見てみましょう。

出典: 建設業を巡る現状と課題|国土交通省
1997年のピーク時以降、建設業で働く人の数は減少傾向にあり、2022年には「3割以上が55歳以上、29歳以下は1割」となっています。
29歳以下が1割以下に留まっている理由として、建設業務は業務負荷が大きく、労働時間も長いといった過酷なイメージがあり、若年層から敬遠されているからだと考えられます。
その結果として比較的高齢の労働者に負荷が集中し、残業時間の削減が困難になっているといえるでしょう。
3.建設業の残業規制改正で何が変わるのか

建設業の残業規制改定によって、2024年4月1日以降は36協定を締結しても原則として「月45時間・年360時間」、特別条項では「複数月の平均80時間、年720時間以内」が上限となります。
この章では、改正前後で何が変わるのか、違いをわかりやすく見ていきましょう。
①2024年4月から残業時間の上限規制が適用
| 改定前 | 改定後 | |
|---|---|---|
| 規制内容 |
特別条項付き36協定締結により、以下のルールが適用。
・1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させることができる。ただし、原則として時間外労働の上限は月45時間・年360時間 ・毎週1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日に労働させることができる ・時間外労働が⽉45時間を超えることができる月は、年6回が限度。ただし、上限時間は実質なし |
特別条項付き36協定締結により、建設業でも以下ルールが適用。
・時間外労働が年720時間以内。 ・時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満x ・時間外労働と休⽇労働の合計について、2~6カ月の平均が全て80時間以内。 ・時間外労働が⽉45時間を超えることができる月は、年6回が限度。 |
| 罰則 | なし。 | 6カ⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科されるおそれがある。 |

②改正後は罰則付きの規制に
改訂前の時間外労働の上限は、厚生労働大臣の告示により定められたものであるため、強制力はありませんでした。
しかし、法改正により改正労働基準法に具体的な数字の上限が明記されたため、罰則付きの規制になったのです。
違反すると6カ⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科される恐れがあります。
※ただし災害からの復旧・復興の事業に関しては、月100時間未満、2〜6カ月平均80時間内の2つの規制は、2024年4月以降でも適用されません。
4.建設業の残業規制へ対応するための4つのポイント
次に残業規制に対応するための課題と対策について4つ紹介していきます。
①正確な勤怠管理の実施
建設業では、従業員が打刻したデータや出勤簿を元に人件費や工数管理などを計算していきます。
しかし、毎月の出勤簿の提出日にまとめて記入を行い提出する人も少なくなく、記入ミスが発生することもあります。
作業現場で作成した日報を勤怠管理として残す場合もありますが、データの改ざんや虚偽申告なども可能なため客観性も信頼性も乏しいのが現状です。
厚生労働省が出している「労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、解決策としてタイムカードやICカードの活用が挙げられています。
②業務効率化の促進
業務効率化の促進に取り組む必要もあります。
日々の業務の中に潜むムダを洗い出して、業務効率化による生産性の向上を図りましょう。
具体的に活用できるツールとして、たとえば以下が挙げられます。
| 建設業で業務効率化につながるツールの例 | ||
|---|---|---|
| チャットツール | 社内や現場関係者との業務連絡に使う。電話連絡や、紙のメモ、伝言から切り替える。業務連絡をテキストメッセージで簡潔に伝え、タイムスタンプと送信履歴が残る。「言った/言わない」などの伝達ミスを低減できる。 | |
| オンラインストレージ | 業務に必要な文書や見積書、請求書、現場写真、図面などをインターネット上で一元管理できる。インターネットに接続できればモバイルやタブレットからでも必要なデータにアクセス可能。紙に印刷する手間を省くことができる。 | |
| ワークフローシステム | 社内稟議や、各種申請を上げて承認してもらうフローをデジタル化でき、紙やハンコを廃止できる。インターネットに接続できればモバイルやタブレットからでも確認可能。承認フローをスピードアップできる。 | |
| ドローン | 現場での測量に使う。ドローンが地形に関するデジタルデータを取得し、データをもとに効率的に設計・施工ができ、工期短縮になる。 | |
③柔軟な働き方の導入
柔軟な働き方の導入も検討してみましょう。
たとえば事務員のリモート勤務を可能にする、技術者のローテーション勤務体制を取り入れる、などが挙げられます。
従業員が「プライベートと仕事を両立しやすい」と長期的に感じられるように、働きやすい職場環境づくりを目指しましょう。
従業員ひとりひとりが長期的に働き方に満足していれば、離職率低減に寄与します。
また新たな人材を迎え入れるための採用活動でも、自社の強みとしてアピールできるでしょう。
④施工管理アプリの活用
建設業における長時間労働の背景には、高齢化や人手不足が要因としてあります。
そこで、業務の効率化を行うために施工写真や図面の管理、工程表などの施工管理業務の効率化が行える「施工管理アプリ」を導入する企業が増えています。
近年、建設業で目にするようになった「建設DX」などは、”ITツールを導入して環境に合わせて働き方を変えていく”という取り組みですが、施工管理アプリもITツールの一つです。
施工管理アプリを活用することで、業務効率化ができ、生産性の向上につながります。
業務上、重要な情報の共有をデジタル化できれば、時間や場所の制約を取り払って、より柔軟な働き方も可能になります。
施工管理アプリは、低価格で始めることが可能で、導入した施工会社の中には「メールの利用が8割減少」という方もいるため、これから業務の効率化を目指す方にはオススメのツールです。
施工管理アプリ「現場クラウドConne」導入事例はコチラ >>関連リンク: 無料版あり|建設現場で活躍する代表的な施工管理アプリ7選を徹底比較
5.建設業で残業規制以外にも注意すべき変更点

ここまで労働基準法改正による残業規制について紹介してきましたが、実は残業規制以外にも注意すべき変更点があります。次は注意すべき3つの変更点を紹介していきます。
①週休2日制の促進
国土交通省では、建設業の働き方改革を推進する観点から直轄工事において、週休2日を確保できるよう、適正な工期設定や経費補正を実施しています。
2024年4月の時間外労働規制の適用に先駆け、2023年度には原則全ての直轄工事で週休2日に取り組む方針を明らかにしました。
②法定割増賃金率の引き上げ
2023年4月1日より、割増賃金率の引き上げが行われました。
| 2023年3月まで 月60時間以下 |
2023年3月まで 月60時間超 |
2023年4月から 月60時間以下 |
2023年4月から 月60時間超 |
|
|---|---|---|---|---|
| 大企業 | 25% | 50% | 25% | 50% |
| 中小企業 | 25% | 25% | 25% | 50% |
割増賃金となるのは時間外労働のみで、休日労働と深夜労働の割増賃金率には変更ありません。
月60時間までの時間外労働であれば今までと変わりませんが、超えてしまうと人件費が上がるため注意が必要です。
③正規雇用者・非正規雇用者の同一労働同一賃金
2020年4月に大企業、2021年4月に中小企業で適用されている「同一労働同一賃金」は建設業でも適用されています。
同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者や非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)といった雇用形態に関係なく、同じ仕事内容に対して同一の賃金を支払うという考え方です。
人件費が上がるのはもちろん、手当なども雇用形態に関係なく支払う必要が出てくるため、見直しが必要になります。
6.建設業における残業規制についてQ&A
最後に時間外労働の規制について、よくある質問を紹介していきます。
Q.現場への移動時間は労働時間に含まれるか?
パターン①:直行直帰の場合
直行直帰の場合は、現場への移動時間は労働時間とみなさず通勤時間になります。
パターン②:上司の指示で一度会社で集合し、車を乗り換えて現場へ行く場合
会社からの指示があるため、会社から現場までの移動時間も労働時間として捉えられます。
Q.週休2日制は義務化される?罰則はある?
週休2日制は法律ではないため、罰則はありませんが、国土交通省は原則全ての直轄工事で週休2日に取り組む方針です。
7.まとめ
今回は、2024年4月から建設業でも適用される時間外労働の残業規制について紹介してきました。
残業規制の適用は、業務効率化を考えるキッカケとなり建設業全体の生産性の向上が期待できます。
また、働きやすい環境は人手不足の解消にもつながります。
もし業務効率化について、何から始めれば良いのか迷ったときは、手軽に始めることができる施工管理アプリ「現場クラウドConne」がオススメです。
無料で始めることも可能で、はじめてでも安心のサポート体制があり、お客様満足度94%の施工管理アプリです。
ご関心がありましたら、ぜひお気軽にお問合せください。
建設業の働き方改革につながる施工管理アプリ「現場クラウドConne」はこちらから! >>

https://romukanri.jp/
6年4ヶ月間の社会保険労務士事務所勤務、3年間の民間企業経営幹部を経て、平成3年4月に社労士・行政書士事務所開業。行政書士・社会保険労務士・特定社会保険労務士付記を保有しており、中小企業庁委託事業として中小企業等をサポートしています。