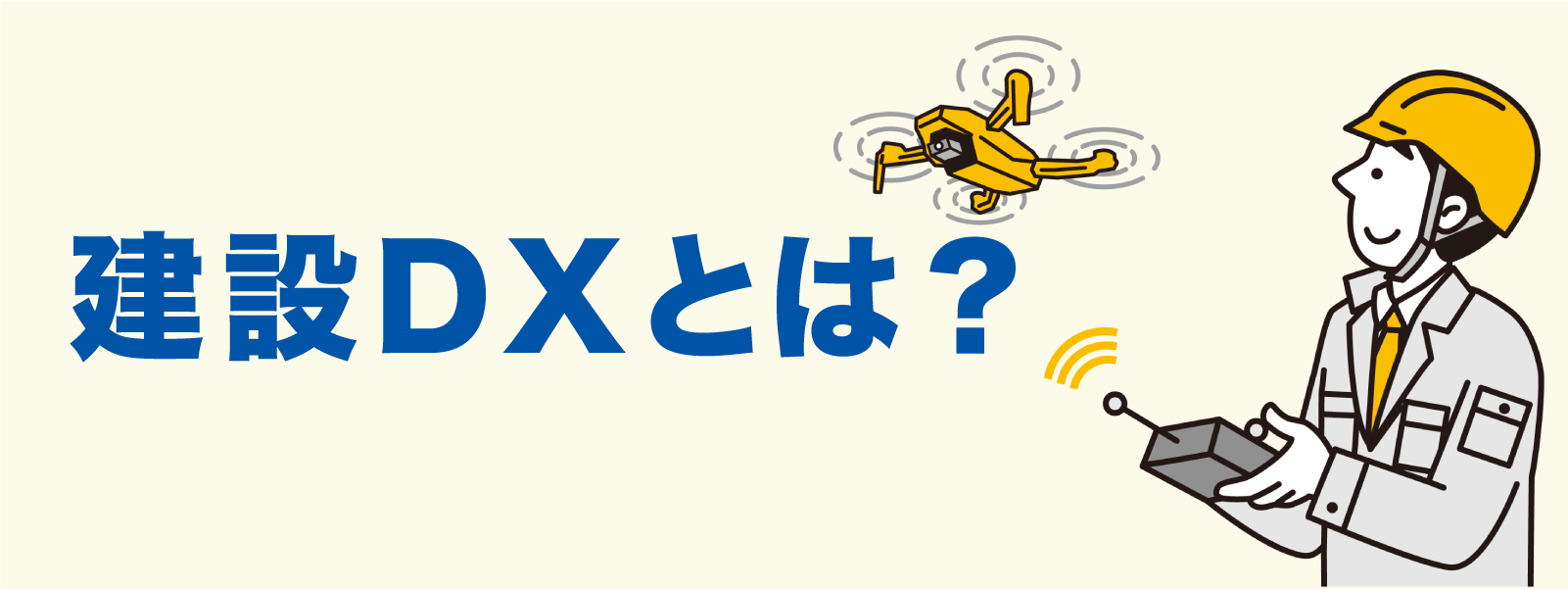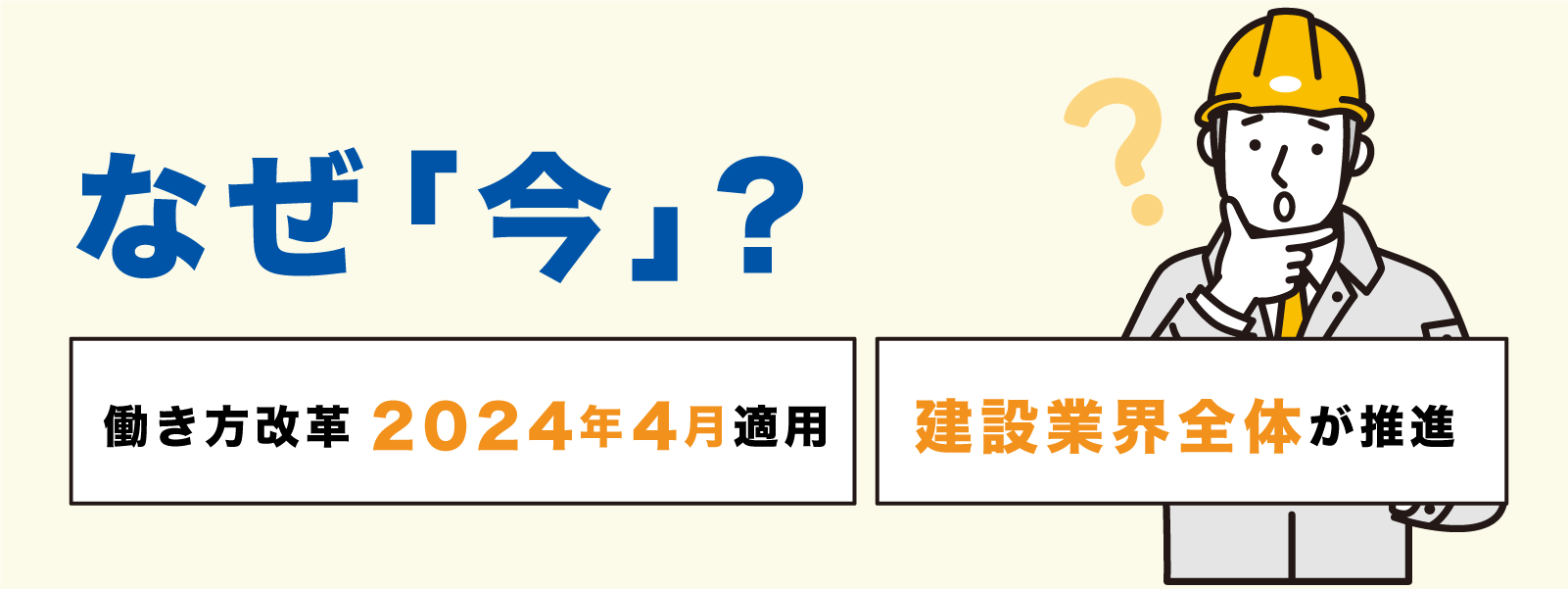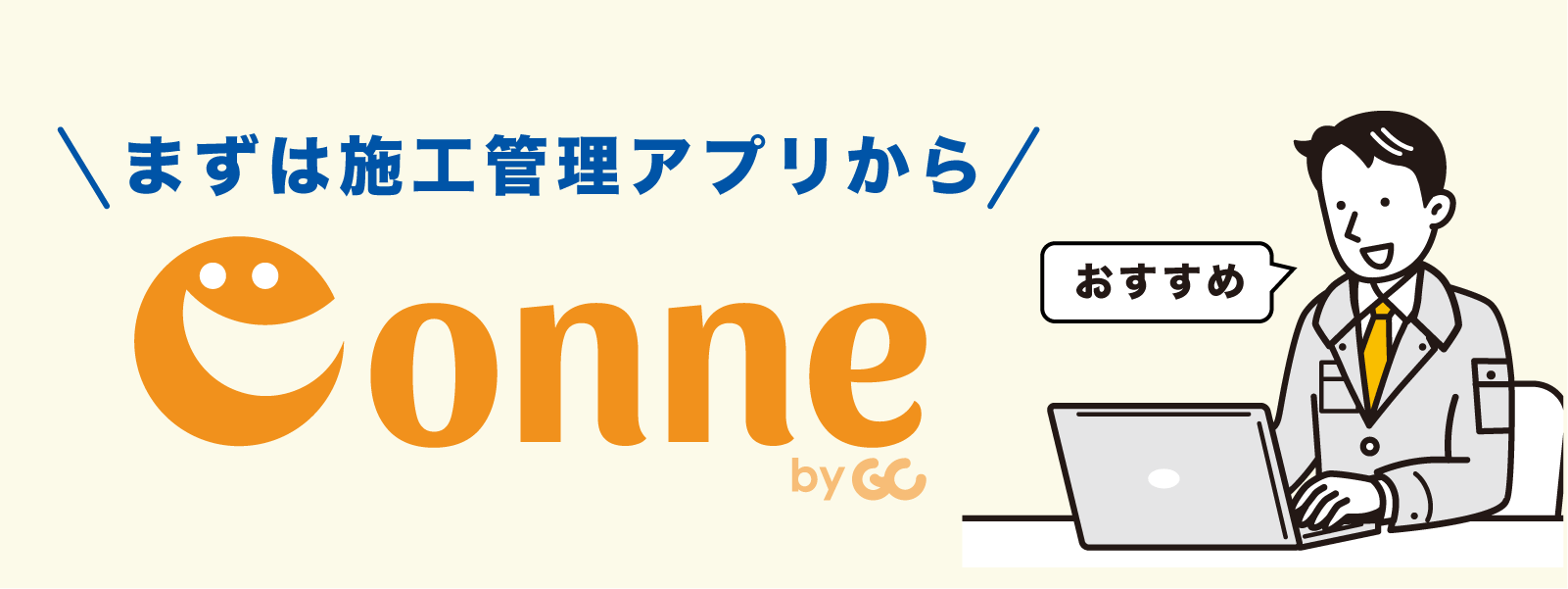建設業界では、人手不足や高齢化による担い手不足などが深刻な問題になっています。
そのような状況を払拭するために、IT技術を活かした「建設DX」と呼ばれる取り組みが期待されています。
皆さんも聞いたことや見たことがあるのではないでしょうか。
しかし『具体的に何に取り組めばいいのかが分からない』『ウチの社員がIT技術を活用できる気がしない』『導入や推進のハードルが高い』といった理由で、建設DXを取り組む前に諦める会社は少なくありません。
そこで、今回は建設DXについて興味はあるものの、まだ取り組む前の方や、取り組んだが上手くいかなかった方が参考になるように、具体的な事例を交えつつ建設DXに取り組む際のポイントをご紹介していきます。
目次
1.建設DXとは
2.なぜ「今」建設DXが求められているのか
3.建設DXの代表的な技術
4.建設DXのメリット
5.建設DXの具体的な成功事例
6.これから建設DXを取り組むときのポイント
7.施工管理アプリは手軽に行える建設DXの第一歩
8.建設DXをはじめるなら
9.まとめ
1.建設DXとは
DXはデジタルトランスフォーメーションの略語です。まずはDXについて解説します。
DXの定義
経済産業省は2018年に「DXレポート」や「DX推進ガイドライン」を公表しており、その中でDXを下記のように定義しました。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
引用元:DX推進ガイドライン(経済産業省)
つまり、急激な市場の変化に対応する為に、クラウドやAIなどのIT技術を活用し、これまで行われていた仕事への考え方や働き方を変えていこうとする取り組みのことです。コロナ禍の影響もあり、さらに注目度が高まっています。
建設DXとは
建設業界で行うDXのことを『建設DX』と呼びます。近年では、ゼネコンから地方の中小企業まで、通信技術を活かしたICTの活用やIT技術の導入などのDXに取り組む施工会社が増えています。
2.なぜ「今」建設DXが求められているのか
DXを始めようとしてもIT技術の導入には、それなりの負担がかかります。二の足を踏む企業も多いのではないでしょうか。ただし、DXを始めるなら「今から」がオススメです。その理由を解説します。
働き方改革の期限
改正労働基準法第36条の5項である「時間外労働の上限」が大企業は2019年、中小企業は2020年に適用されていました。2024年の4月からは災害の復旧・復興の事業を除き、全ての建設業界にも適用されます。違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則(刑事罰)に科される可能性があります。
既に時間外労働の上限を超えている施工会社は、あと数年以内に建設DXに取り組み、働き方改革関連法案が適用された時点で上限を守れている状態である必要があります。
また、日頃は時間外労働時間が守れている施工会社でも、繁忙期に超えてしまう危険性もあります。
そのような状況下で直前になって建設DXを始めても、導入効果が直ぐに現れにくいため2024年の4月までに間に合わないかもしれません。そこで、少し余裕を持って「今から」始めることをオススメします。
建設DXへの後押し
もう一つの「今から」建設DXを始めるべき理由としては、建設業界全体が建設DXを推し進めている点が挙げられます。
本記事の冒頭でも紹介しましたが、国土交通省が「インフラ分野のDX」を唱え、省内や地方整備局の組織体制が変わってきました。一部の公共工事ではBIM/CIMの活用が義務化されるようになり、3次元モデルの活用なども増えてきました。
政府もICT技術を活用して生産性の向上を図るi-Construction(アイ・コンストラクション)を積極的に推進しており、建設業界がIT技術を活用して変わろうとしています
令和3年度には、IT導入補助金などが含まれる生産性革命補助金として約2,000億円の予算が確保されており、補助率の引き上げなども行われています。※1
※1:参考文献『中小企業庁関係 令和3年度補正予算のポイント』
3.建設DXの代表的な技術
では、建設DXではどのような技術が使われているのでしょうか? ここからは建設DXの代表的な技術をご紹介します。
クラウド
クラウドは、インターネット環境さえあればどこでも利用可能です。距離に関わらずリアルタイムに工事情報の共有が行えます。施工写真や図面の管理、工程表や日報などの施工管理業務をスマホやパソコンで一元管理できる『施工管理アプリ』などもクラウドの一つになります。
ICT(情報通信技術)
ICTとは、Information and Communication Technologyの略で、人とインターネットを繋ぐことで、人と人を繋ぐ技術のことです。リモートグラスを用いたリアルタイムなコミュニケーションを行い、若手技術者支援の体制を整えることが可能です。AR技術を使った設計図の現場共有や、ドローンによる3次元モデルの生成なども行っています。
IoT(モノのインターネット)
IoTとは、Internet of Thingsの略で、あらゆるモノがインターネットに繋がりデータの取得を実現する技術です。現場にある様々なモノがインターネットに接続されることで、位置情報や気候の状態、作業員の体調まで把握できるため、建設現場の生産性向上が期待できます。
AI(人工知能)
AIの活用によって人手不足を解決していく企業も増えてきました。単純作業の自動化を実現できることや、安全性の向上も期待できるため、建機の自立走行や画像認識技術を活かした判定システムなどの導入が行われています。
4.建設DXのメリット
建設DXはどのようなメリットがあるのでしょうか。取り組むことで得られるメリットについてご紹介していきます。
人手不足の改善
建設業界は深刻な人手不足に悩まされています。ドローンや自立型建機の導入により現場の負担が軽減され、現場の労働環境が改善されます。特にAI技術の導入などは、少人数化しても安定した成果を出せるようになるため、人手不足の解決に繋がると注目されています。
効率的な業務
国土交通省の現場で既に用いられている遠隔臨場などを導入すると、現場に行かなくても立ち合いが可能にな、移動時間が軽減されます。また、施工管理アプリを導入すると工事関係者との段取りの行き違いなどが起きにくくなるため、効率的な現場運営を行えるようになります。
技術の継承
専門的な技術が必要な建設業界の業務は、熟年技術者と一緒に経験をして技術力を身に付けていく必要があります。しかし、近年では技術者を志す若手も少なく、折角入ってきた若手も技術を伝えきる前に辞めてしまうこともあります。
建設DXが進めば、デジタルツールを活用してマニュアルを作成したり、熟年技術者の知識や技術をデータとして蓄積したりできるため、若手の育成や技術継承者が途絶えてしまう問題などを解決できる可能性があります。
安全面の向上
危険な場所での作業は命に関わることもあります。デジタルツールや通信技術を活用できれば、万一トラブルが起きても人が巻き込まれる危険性を減らせます。バックホウの自律運転システムなどを活用すれば、オペレーターは離れたところから操作が可能で、安全な場所からトンネルの掘削などが行えるようになります。
競争力の強化
建設業界はITリテラシーが高い方ばかりではありません。その中でも建設DXを進めることができれば競争力の強化に繋がります。建設業界で言われている「3K(キツイ・キタナイ・キケン)」も改善されるため、社員満足度や定着率の向上にも繋がります。労働環境の改善は採用にも影響を与えます。有力な人材を採用できれば、さらに建設DXは進み、競争力も強化されるでしょう。
>>無料で使える施工管理アプリ『現場クラウドConne』はこちらから!
5.建設DXの具体的な成功事例
実際に、建設DXに成功した事例をご紹介します。
株式会社上東建設 様
『遠隔臨場の導入で、コロナ禍でも安心の現場確認!』

株式会社上東建設様は、新型コロナウイルスまん延防止等重点措置が延長され、現場での臨場検査が行えなくなったことより、今後の公共工事での活用も見据えて遠隔臨場を導入しました。導入後は、コロナ禍でも安心して臨場検査を行えるようになりました。対面での確認とは違い発注者が画面に映る情報に集中する分、より整理整頓や安全面への配慮にも繋がりました。
佐多エンジニアリング株式会社 様
『現場の状況をリアルタイムに把握できるように。社員同士の情報共有も活性化。』

佐多エンジニアリング株式会社様は、遠方の現場に出ている社員との情報の質を改善したいと考え、クラウドサービスを導入しました。導入後は、スマホやパソコンで簡単に現場の進捗が把握できるようになり、社員同士の情報共有も活発になったことでトラブルの未然防止や対応スピードの向上に繋がりました。
堤工業株式会社
『ノンストレスで大容量データの共有を実現し業務を効率化。』

堤工業株式会社様は、工事に関するデータ等を本社のNASで管理しており、現場などの遠隔地からでも本社のNASにアクセスできるようにしていました。しかし、通信環境が不安定な時もあり、確認に時間がかかっていたためクラウドサービスを導入しました。導入後は、どこからでも必要な時にサクサクとアクセスができるだけでなく、入札した案件情報の共有や、進行している現場情報の共有などが行えるようになりました。現場からでも社内の動きが把握できるようになり、大きな業務効率化に繋げています。
福山総合建設株式会社
『ISO審査員からも高評価!パソコンが苦手な人を考慮した運用の工夫で業務効率化を実現。』

福山総合建設株式会社様は、元々社内でグループウェアを導入していたのですがなかなか定着せず、少数しか使われない状況でした。そこで、代わりとしてシンプルで分かりやすいクラウドサービスを導入しました。多機能ではなく、機能を絞り込んだサービスに変えたことで、反対に活用が広がり、現場の見える化や新入社員教育の活性化、知識の共有も進んだためISO審査員から高評価を頂くほどに変化しました。
6.建設DXを取り組むときのポイント
次に、建設DXに取り組む際に気を付けて欲しい3つのポイントをご紹介していきます。
POINT➀:現場とのギャップ
経営陣と現場の乖離が起きないように注意しましょう。経営陣は短期的な売上増加に直結するITソリューションを導入しようと考えますが、実際に現場で使う社員が感じている課題を解決できなかったり、現場が使い難いと感じるシステムではいくら便利なシステムでも建設DXは一向に進みません。お互いに何が必要なのかを整理する必要があります。
POINT②:導入コスト
ICT施工を進めようとした場合、必要な機材や建設機械は高価なものが多いです。システムによっては初期コストが数十万円~数百万円もかかるケースもあり、メンテナンスなどの維持コストも別途かかることもあります。導入するシステムによっては、投資に対する効果が見合わない可能性も出てきます。
POINT③:利用ハードルの高さ
多機能なシステムを導入した会社では、社内浸透するまで何度も勉強会が必要なことも多く、同時進行で運用方法や運用ルールまで細かく担当者が決めていく必要があります。そのため、導入担当者への負担がかなりのものになります。その結果、社内浸透まで時間がかかり過ぎ、使いこなせない人が出てきてしまい、導入した効果が得られないことがあります。
7.施工管理アプリは手軽に行える建設DXの第一歩
建設DXの気を付けるポイントを見て少しでも不安を持たれた方は、施工管理アプリから始めることをオススメします。施工管理アプリがオススメな理由として次の3つがあります。
現場や業務のニーズに合わせたアプリが豊富
施工管理アプリは、業種・業務内容に合わせて作られたサービスが多いので、現場の方が実際に利用して「痒い所に手が届く」と感じるようなサービスが多いことが特徴です。業務ごとのニーズに合わせてサービスを選ぶことで、現場とのギャップを最小限に抑えることもできます。
クラウドサービスならではの手軽さ
施工管理アプリは、導入コストが比較的低いです。クラウドサービスなので、ネット環境があれば手軽に始めることが可能で、細かい設定も不要です。退会するときもすぐに退会できます。アプリによっては完全無料のサービスもあり、有料のサービスでもお試し期間などが設定されていることも多く、導入ハードルの低いものが多いです。
パソコンが得意ではなくても利用できる簡単さ
施工管理アプリは、誰でもスマートフォンやパソコンで利用できるように作られているため、直感的に使えるサービスが多いです。アプリによっては、サポート体制を強みとしているサービスもあるため、パソコンが得意ではない社員が多くても安心して導入いただけます。
8. 建設DXをはじめるなら
施工管理アプリを始めるなら現場クラウドConneがオススメです。
オススメする理由は、次の通りです。
➀最も重要なコミュニケーションを活性化
建設現場では工事関係者と連携を取りながら施工を進めて行きますが、建設DXを進める際も同様に、社員同士が連携を取りながら働き方の変革を進めなければ、どんなに素晴らしいサービスを導入しても効果は出ません。
現場クラウドConneは、社内や協力会社との連携を行うときの土台であるコミュニケーションを支えるサービスになります。コミュニケーションが円滑になることで、建設DXを進めやすい環境を作ることができます。
②無料で使えるプラン&誰でも使えるシンプルな画面
いきなり有償版を導入するのはハードルが高いと感じる方向けに、無料で使えるプランもあります。使える機能は有償版とほとんど同じで、期限もないので安心して試験的に導入できます。
機能の種類はシンプルで、お客様の声から必要な機能だけを集めた機能しかないので、パソコンが得意でなくても迷わずに直感的に使えます。
③建設業を熟知したサポート体制
現場クラウドConneのサポート体制は、建設業を熟知したサポートメンバーが、お客様に合わせて運用提案から社内勉強会の段取りまで全力でサポートする体制です。導入初期から本格運用まで、社員全員が使えるようになるまでサポートするので、安心して導入ができます。
>>無料版あり|建設現場で活躍する代表的な施工管理アプリ7選を徹底比較
9. まとめ
今回は建設DXの具体的な事例と、始める際のポイントについてご紹介しました。
建設DXは単にクラウドなどのIT技術を導入するだけではなく、これまで行われていた仕事への考え方や働き方そのものを変えていこうとする取り組みで、どうしても時間が必要になります。
その分、上手く取り入れることが出来れば、組織力や競争力が向上します。働き方改革関連法案の適用が迫っている今だからこそ挑戦するタイミングといえるでしょう。
弊社が提供する現場クラウドConneは、建設DXの第一歩としては比較的取り組みやすいサービスです。これを機に、建設DXを始めてみてはいかがでしょうか。