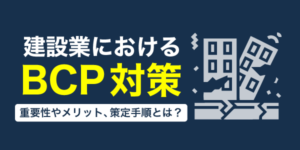建設ディレクターとは、ITとコミュニケーションスキルで建設現場を支援する新しい職域のことです。
工事施工に関する書類作成やICT業務を担い、現場とオフィス、経営をつなぐ役割があります。建設ディレクターの導入によって、若手や女性従業員などが最新のスキルを身につけながら、やりがいを持って建設会社で働けるようになります。
また、職人は本来注力すべき現場業務に集中でき残業時間の削減につながるなど、さまざまなメリットがあります。
この記事では建設ディレクターの役割や仕事内容、今求められている理由、具体的な導入メリット、導入事例などをご紹介します。
目次
1. 建設ディレクターとは
2. 建設ディレクターの役割と仕事内容
3. 建設ディレクターを導入するメリット
4. 建設ディレクターの導入事例
5. 建設ディレクターの導入を成功させるポイント
6. 建設業の情報共有を促進するアプリならConneがおすすめ
7.まとめ
1.建設ディレクターとは

建設ディレクターとは、ITとコミュニケーションスキルで建設現場を支援する新しい職域のことです。
建設ディレクターの育成を担う「一般社団法人建設ディレクター協会」によって創設されました。
建設ディレクターは、工事施工に関する煩雑な書類作成やICT業務を行い、現場とオフィス、経営をつなぐ役割を持ちます。
建設ディレクターを配置することで現場監督・職人は、本来注力すべき現場業務に集中でき、長時間労働の軽減を期待できます。
また建設ディレクターという職域の導入によって、若手や女性従業員の安定雇用や、ポータブルスキルの獲得につながるなど、多くのメリットが挙げられます。
①建設ディレクターが求められる背景
建設ディレクターという新たな職域の創設により、建設業界の課題解決につながると期待されています。
建設業における現状の課題として、少子高齢化によって若手を中心とする人手不足が進んでいる点や、建設業でもIT化が加速しているにもかかわらず、ITツールを苦手とする人が多い点が挙げられます。
さらには2024年4月から「働き方改革関連法」が建設業にも適用され、時間外労働の上限規制によって長時間労働ができなくなりました。この新ルールに違反すると罰則が科されるため、建設会社は残業時間の削減に向けた取り組みに着手しなくてはなりません。
そこで専門知識を身につけた建設ディレクターが、ITツールを活用しながら職人の負担となっている書類作成などの業務を担うことで、業務効率化や生産性向上につながります。
実際、建設ディレクターを導入して書類業務を担当してもらうことで、月に30〜40時間の残業時間を削減できた事例もあります。
また建設ディレクターの導入は、デジタル世代の雇用創出や女性活躍を加速させる点もメリットです。最新のICTスキルを身につけながら、若手や女性もやりがいを持って建設会社で働けるようになると期待されています。
関連リンク
建設業の2024年問題とは?影響や対策をわかりやすく解説
②建設ディレクター制度のプログラム
一般社団法人建設ディレクター協会が提供する、建設ディレクター制度のプログラムには、「育成プログラム」「活躍プログラム」「定着プログラム」の3種類が用意されています。
このうち「育成プログラム」で実施されている「建設ディレクター育成講座」を受講して、テストに合格すると「建設ディレクター認定証」が発行されます。
この受講には厚生労働省の助成金を利用することが可能で、自社負担額を抑えて学ぶことができます。
2. 建設ディレクターの役割と仕事内容
次に、建設ディレクターの役割と仕事内容を詳しく見てみましょう。
①役割
建設ディレクターには、以下の3つの役割があります。
1. 生産性向上
2. 女性が活躍する職場の実現
3. 職場とオフィス、経営を結ぶ
ITスキルを身につけている建設ディレクターは効率的に書類を作成でき、現場の負担が軽減するため生産性向上に役立ちます。また建設ディレクターの7割が女性で、建築業界における女性の活躍を後押しする役割があります。さらに建設ディレクターが継続的に支援することで、現場とオフィス、経営をつなぎ社内の仕組みを整える重要な役割も担っています。
②仕事内容

建設ディレクターの仕事内容は、大別して以下の2種類に分けられます。
1. 書類作成
2. ICT業務
ただし個々の業務内容は建設会社によって異なります。ここでは一般的な仕事内容を見てみましょう。
1)書類作成
建設ディレクターの仕事内容として、書類作成が挙げられます。
建設業で取り扱う書類には数多くの種類があり、たとえば職人は以下の書類を作成する必要があります。
● 入札・着手に必要な書類
● 施工体制台帳の作成
● 図面修正
● 補助金・助成金の申請
● 安全書類
取り扱う書類の数は多岐にわたり、職人は現場業務だけではなく書類対応にも追われている状況です。
そこで職人でなければ対応できない書類業務と、標準化できる業務をあらかじめ切り分けておき、後者を建設ディレクターが担うことで、現場監督・職人の業務負荷を軽減できるでしょう。
2)ICT業務
建設ディレクターが担うICT業務として、ドローンを活用した3D測量が挙げられます。
ドローンの操縦資格を保有した人材を採用・育成することで、これまで2人で対応していた測量を建設ディレクター1人で完結できるようになります。
国土交通省が実施する「i-Construction」ではドローンによる3D測量などが推進されていますが、中小企業では取り入れるのが難しい側面もあります。現在では、高校でドローンの授業があり、操縦資格を保有する若手人材もいるので、新しい技術を任せることで生産性向上を期待できるでしょう。
3. 建設ディレクターを導入するメリット
ここからは、建設ディレクターという新たな職域を導入する3つのメリットを解説します。
①現場監督・職人の業務負担が軽減する
これまで現場で職人が担っていた業務を建設ディレクターが担当することで、現場監督・職人は業務負担や残業時間を減らすことができます。
一般社団法人建設ディレクター協会が、現場業務の移管率について調査したところ、建設業の仕事の6割は書類作業で、現場が抱えている業務の多くを建設ディレクターに任せられることがわかっています。
現場監督・職人は空いた時間を使って、品質管理や技術継承などのコア業務に専念できるようになるでしょう。
②若手・女性人材の獲得につながる
建設ディレクターの創設は新たな雇用を生むため、若手・女性人材の獲得につながると期待できます。
現在、建設ディレクターの数は約900名で、その7割が女性です。また、20〜30代が65%を占めています。
たとえば地元の建設会社で建設ディレクターの職を新規創設すると、地元に残って就業を希望する若手・女性人材にとって新たな働き口となります。ICTなど最新のスキルを身につけてやりがいのある仕事ができるので、一度獲得した人材が定着しやすくなるでしょう。
また働き手の立場ではポータブルスキルが身につくので、就業途中で家族の都合で引っ越すことになっても、転職先を探しやすくなります。
③業務標準化が進む
建設ディレクターが現場に関わることで、業務の標準化が進むと期待できます。
これまでの社内書類業務では、個人によって作成方法やフォーマットが異なる場合も見られました。しかし建設ディレクターが建設現場のバックオフィスで職人とワークシェアをすることで、書類作成の効率化だけでなく、業務の属人化が解消されます。
また建設ディレクターが複数の現場に携わり、社内で良い取り組みを共有することでオペレーションが改善され、会社全体の生産性向上にもつながるでしょう。
建設業の情報共有が促進されるアプリ『現場クラウドConne』はこちらから!
4.建設ディレクターの導入事例
国土交通省による「建設業における働き方改革推進のための事例集」でも、建設ディレクターが紹介されています。ここでは、2つの事例を見てみましょう。
出典
建設業における働き方改革推進のための事例集|国土交通省
①建設ディレクターの導入で長時間労働を是正|株式会社⻄九州道路
佐賀県の舗装工事会社「株式会社西九州道路」では、長時間労働が常態化していました。現場監督の業務負担が大きく、労働時間の削減が急務だったといいます。
全業務を現場監督が担うことが多かったため、文書作業など比較的他者に任せやすい業務を建設ディレクターに振り分けました。
その結果、現場監督は本来の業務に集中できるようになり、長時間労働が是正され、さらに現場と総務部門など部署間でのコミュニケーションがスムーズになりました。
②建設ディレクターがバックオフィス業務を支援|鹿児島県の建設会社
鹿児島県に拠点を置く建設会社では、建設ディレクターを導入し、長時間労働の削減に成功しています。
建設ディレクターは、とくに工事に関連するデータの整理、処理、提出書類の作成など、バックオフィス業務を支援しています。また施工計画書の作成や、写真整理なども担当しています。
このような業務の切り分けによって、現場作業終了後の書類作成時間が削減され、現場監督やスタッフは会議や現場作業に集中できるようになりました。
5.建設ディレクターの導入を成功させるポイント
続いて、建設ディレクターという新たな職域の導入を成功させるための2つのポイントを解説します。
①現場サイドと連携したチームづくり
まずは、現場サイドと建設ディレクターが緊密に連携できるチーム作りが重要です。そのために、建設ディレクターに依頼する業務を定義する必要があります。
導入当初から、これまで職人が担っていた書類作成業務のすべてを移行するのは難しいかもしれませんが、難易度に合わせて徐々に任せていくと良いでしょう。
建設ディレクターと現場の間に、現場や技術面の詳細がわかる橋渡し役の担当者を配置するなど、業務フローを工夫するのもおすすめです。
②使いやすい情報共有アプリの導入
現場監督・職人と建設ディレクターが協力して業務を進めていくためには、社内の誰もが使いやすい情報共有アプリが必要です。
建設業界向けの情報共有アプリを導入することで、社内のコミュニケーションが活発化するメリットがあります。
たとえば毎日の連絡事項、タスク一覧、資料や議事録、マニュアルなどを情報共有アプリ上で一元管理しておくと効果的です。社内の誰もが同じ資料やデータを見て会話ができれば、認識や指示の行き違いを防止できて業務進行がスムーズになります。
関連リンク
【比較表あり】建設現場でおすすめの情報共有ツール8選!無料で使えるアプリも
6. 建設業の情報共有を促進するアプリならConneがおすすめ
現場関係者間の情報共有を推進するアプリとして「現場クラウドConne」がおすすめです。Conneの機能の特徴は、次のとおりです。
● 部署や現場関係者ごとに、アプリ上で情報共有ができる
● 写真や図面など、大容量のファイルもクラウド上で一元管理できる
● 重機や機材、社員や現場の予定を共有できる
● Conneに招待すれば、社内外を問わずスペースやチャットでコミュニケーションが取れる
● 案件ごとの進捗状況を一覧化できる
このように現場関係者の情報共有がスムーズになるConneがあると、建設ディレクターは現場の状況を適切に把握でき、職人との連携がより円滑になります。
①【事例】関係者とのコミュニケーションが改善|MBC開発株式会社

鹿児島の企業「MBC開発株式会社」は、「現場クラウドConne」の導入によって、施工管理業務の効率化を実現しました。
現場の状況をアプリ上で可視化し、協力会社とのコミュニケーションを簡略化することで業務効率が向上。また電話やメールを使用する頻度が大幅に減少し、情報共有がスムーズに行えるようになりました。
②【事例】情報共有のスピードが向上|明治建設株式会社

熊本の建設会社「明治建設株式会社」は、「現場クラウドConne」を導入したことで、社内の情報共有のスピードが向上しました。
Conneに資料置き場や部門・現場別のスペースを作成し、社内資料の電子化と保存を実現。社員がいつでも、どこからでも現場に関する情報を参照できるようになったため、業務の効率が格段に向上し、コミュニケーションの質も向上しています。
7.まとめ
建設ディレクターと呼ばれる新たな職域を導入することで、新たな雇用を創出でき、若手・女性の活躍と定着、そして職人の業務負荷低減を期待できます。
自社でもこの職域を新設し、建設ディレクターの活躍と業務効率化を成功させるためには、「スムーズな情報共有」が鍵だといえます。
現場や技術に関する知識を、建設ディレクター側が適切に理解して書類作成などを進めることができれば、社内全体で業務標準化が進み、長時間労働を抑制できるでしょう。
そのためには、現場に関する情報を透明化して属人化をなくせるよう、建設業に特化した情報共有アプリの活用がおすすめです。下記のサイトからアプリの詳細をぜひご覧ください。